日本の非暴力の政治的市民運動と自由
「幻のダムものがたり」 [
2 ]
歴史家 小林茂氏インタビュー
『幻のダムものがたり』緒川ダム反対住民運動ノンフィクション 1967-2001
クリスチャン・ポーズ:インタビュアー、(吉川真実:訳、茨城県常陸大宮市、2006年12月)
『幻のダムものがたり』 小林茂氏インタビュー [ 1 ] Page
en francais
小林茂氏は、茨城の緒川村、美和村という日本の農村地区に起こったある一つの市民運動について言及しています。
このインタビューは、憲法で守られるべき権利が公的権力によって剥奪された反対住民の無力さと、政治家の放蕩無頼、政治の無策さにも焦点をあてます。

小林 茂 KOBAYASHI SHIGERU,
1931年、茨城県常陸大宮市上小瀬生まれ。
農林業に従事、この間、緒川村議七期、議長、農業委員会会長。
県営緒川ダム問題に取り組む。
現緒川郷土文化研究会会長、茨城県歴史教育者協議会会員。
(写真左:クリスチャン・ポーズ)
·
·
·

『幻のダムものがたり』
- 緒川ダムの三十三年 -
2002年、文芸社

白線内で囲んだ緒川ダム計画、ダムサイトと水没予定地
『幻のダムものがたり』裏表紙より
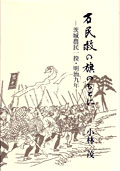
『万民救の旗のもとに』
- 茨城農民一揆・明治九年 -
小林茂著、2006年
-----
※ このインタビューの日本語とフランス語のページは各々編集されており、全くの相互直訳ではありません。
フランス語のページでは、説明のための補助文や追加資料が挿入されています。
補償の問題は、南アフリカ、インド、中国、トルコ、ロシア、ブラジルやラオスでも移転がある場合に持ち上がる問題です。緒川も例外ではありません。世界ダム委員会の知識人たちも、賠償評価や代替提供をすることの優先、先決を要するという点において、小林さんの見方と一致します。この委員会は、この問題に関わる移転民が世界に4000万~8000万人いると見ています。
Q 15 補償金は緒川村、美和村の住民に払われたのでしょうか。
小林 払われなかったです。補償金というのは、ダムの場合、地元の地権者団体と県で補償交渉をして妥結しないと払われないんです。ここ緒川の場合は、交渉まではいったけれどダム計画が中止になったので調停までできなかった。県の方から村を通して払う、地元対策としての補助金はでましたけど、それは補償金とは別なんだよね。だからダム計画の補償金というのはなかった。
・ 住民の不満、要求の聞き入れや補償はどのような手順で進んでゆきましたか。
― ダムの設計書ができあがりましたよね。我々はダムが進むと思ってたから、4つの住民団体が代表を出して補償交渉委員会というのをつくって県の方と話し合いをはじめたんです。ただこの頃県側はダムをつくる気がなくなってたから、こちら側と話が食い違ってくるわけだよね。
・ この補償交渉に関する法律はどのようなものですか。
― どこの国でもダムなり公共事業なりやる時に、用地を確保するのにそこの住民を移動する、代替地の選択など当然補償の問題が出てくるわけですね。国によって違うでしょうけれど、例えば中国の三峡ダム(揚子江)、100万人(実質200万人)が強制移転するような国家権力で進められているダムだけれど、補償金はスズメの涙だろうけど払われてますよね。日本では強制的にというのはできないけどね、民主主義だから。
・ 世界ダム委員会はこの補償問題に重きを置いています。
― 日本でも終戦を境に補償問題が違ってきましたよ。奥多摩に小河内ダムや栃木県の五十里(いかり)ダムは戦前から補償交渉始まっていた。補償といっても国家権力が強かったからスズメの涙。戦後は民主主義だから、保証金の額も上がったし、無理につくることはしなくなった。
ダムは起業者と住民との問題なんだけれど、主導権を握るのは起業者なんですよね。住民は受け身で、住民の代表者が話し合って交渉で決めるわけなんです。一般の道路とかは違いますけど、ダムはそうです。だから細かく、家は一坪いくらで補償します、宅地とか畑とか山とか… それをみんな細かく価値を決めてゆくんです。事業者の方は低く押さえたい、こっちは高く価値をつけたい、なかなか接点が合わないんで、何回も何回も交渉するわけです。
- c 村や県、政府や国会でのダム補償問題に対する討論(質問)を追っていましたか。
― 補償の件を最終的に決めるのは建設省(現国交省)でマニュアルがあるんでしょうね。こういうダムはこのくらいだ…とかね。交渉して妥結するまでには県の方では何回も建設省に問い合わせて、値段を決めてゆくわけ。
・ 補償問題がこじれている時に、国会でそのような法の改正とか調整などするのが役割なのに、なぜ取り上げないのですか。たとえ緒川ダムのような小さなダムの問題でも…。
― なかった。「蜂の巣城闘争」みたいにすごくこじれればね取り上げられるかもしれないけれど。
・ 一国民として社会党や共産党、野党がこういう問題についてどのように扱うのか気になりませんか。
― 野党も具体的な交渉の問題の中には入れない。具体的に地権者のほうは、土地をいくらで買ってくれと、県の方は、それでは高すぎるとか、当事者が交渉しているところに、政党の野党とか与党、与党っていうのは国の方になるわけだよね、それが間に入ってくるっていう事は実際にはないよね。
- d 土地収用法とはどのように向かい合っていましたか。この法律について説明してください。
― ここ緒川ダムは、土地収用法を発動するまでにいかなかった。 一般的には、補償交渉が妥結して賠償交渉になる。今度は個人個人と県側。何十人って土地所有者や関係者がいる中で「オレは絶対いやだ」っていう人がでてくるわけですよ。必ず。入ってくるのも嫌だ、つけられた価値が気に入らないということも含めて、絶対折れない場合には、県の方で土地収用法を発動する。県の収用委員会が「この法律を適用する」と言えばね。
・ 適用されるということは、所有しているものを失うということですか。
― 本人が納得するしないにかかわらず、強制的に収用しちゃう。
・ その場合に補償金は出ますか。
― 補償金は出ますよ当然、強制収用でも。
・ この法律を恐れてましたか。
― もちろん恐いですよ。
それは財産を失うからというよりも、こちらの意志に関わらず強制的に、抵抗できない…それは恐しい事だよね。
・ この土地収用法はいつできたのですか。
― 結構昔になると思います。(旧土地収用法―明治33年―に代わって1951年制定)
・ 補償に関する基準法などはいつできたのでしょうか。
― これも昔からあります。明治になってすぐできたと思う。100年くらい前に。いくら封建といっても徳川の江戸時代から、補償という考え方はあった。殿様でも土地を取り上げるんじゃなく金を払った。「公共用地の取得に伴う損失補償基準」というのが正式な名称なんだけど、この法律によって補償するわけです。第一条の目的として、○○事業に必要な土地等の取得、または土地等の使用に伴う損失の補償の基準。この水準を決めて事業が円滑に進むように適正な補償を確保する事を目的とする…ということなんだよね。建前上はいちおう良い事言ってます。1962年ですね。戦後の民主主義的な法律ですね。
・ 市民反対運動とかが色々起こっていたから…。
― そうですね。もう「蜂の巣城闘争」とかすでに色々あったから、細かく項目をつくったってことは、そういう事も影響しているんだろうね。
・ 1962年というと、利根川水系水資源開発基本計画と同じ年にこの損失補償基準法もつくられています
― 利根川水系(計8ダム)では、群馬の方には八ツ場ダム(吾妻川)、川俣、五十里ダム(鬼怒川)あるでしょう。補償問題というのはやはり難しいんですよね。国は少なくしようと抑える、住民は生活かかってますからなるべく高くもらいたい。
・ 小林さんは、補償問題の手順がより円滑に妥結するようにとか、条約や法の改正とか考えられましたか。
― それはなかった。というよりも、ここのダムは、補償交渉に入る前に、県の方では中止だと決めていたから、向こうは話し合いにも一生懸命にならない。こちらも、なんだか調子がおかしいな、と思い始めた。本格的な話はできませんでした。
- e 水源連や川辺川、長良川、吉野川、徳山など他のダムの犠牲者反対団体とは交流がありましたか。
― 交流はないんですが、清津川ダムとは意見交換があって視察に来た。こちらが時期としては2年くらい早かったんです。ただダムの規模が違う。こっちは600万トン、むこうは3000万トン。
・ 前にも言いましたが、ダムの大小に関わらず、一人一人の住民の受ける苦悩は同じです。ダム建設の被害者団体などとの交流、日本全体のそういった反対者団体の会はあるのでしょうか。
― 犠牲者団体というのはちがうけれど、地権者団体、住民団体…はあるけれど、日本全体を総括するような、全国的なつながりの同盟のようなものはないようですよ。
・ 同盟や委員会のようなものがあればいいと思うんですけど。
― 日本全体のそういう組織があればいいでしょうね。一人一人でやるより、運動がちがうでしょうね。
議員や日本の知識人は、ほとんどの世界ダム委員会の知識人達も同じですが、特別開発プロジェクトの基本は水流域の社会組織を考慮することを認識することです。昭和48年の水源地域対策特別措置法(水特法)はこのような問題をグローバルに鑑みたように見えました。
Q 16 - a 水特法とはなんですか。どのような分析が可能ですか。
小林 ダムの計画によって、住民の生活基盤が失われ、変わってしまう。そういう地域に対して、道路や水道とかいろいろな生活の条件を整えることと、産業基盤、移転したりして働くところを整備して、住民の生活を安定させるためにつくられた法律なんです。
・ 生活面を扱ったグローバルな法律ですね。良い法律ですか。
― ここは適用にはならなかった、ダムが中止になったからね。でも内容は良いと思う。
・ 補償問題の訴訟を考えた時に、この水特法を引き出すことは可能だったのでは。
― 水特法のことは特に訴訟のときは出してなかった。ただ、美和村と緒川村の整備計画はつくりました。結局、この法律の背景には、ダムというのは住民にとっては決してプラスにはならない。立ち退かなければならない、今までまとまっていた集落がバラバラになる、隣近所の付き合いも変わってしまう、就職の問題、農家の人がダムのために農地を失って農業から離れなければならない、就職して外で働くけれど、思うようには行かない… というようにマイナス面が多いんですよ。昭和48年にこの法律ができたころは、ダム反対運動がすごく盛んだった。『幻のダム…』の108ページに書いてあるんだけど、栃木の湯西川今でもやってます、南摩、群馬の八ツ場、福島の三春、真野(まの)、埼玉の浦山、合角(かっかく)… 個人の財産を補償しただけでは済まなくなってきた。住民の権利意識が高まってきたから。それを解決するためには総合的に良くしなければだめだという考え方になってきたからね、それで水特法ができたわけだよね。この緒川ダムは、平成元年に国の政令指定になったんだけど、これには基準があって、水没家屋が30戸以上で、それ以上小さいダムは指定になりませんけど、水没面積が何ヘクタール以上とか。緒川ダムは対象の中に入っています。
- b 建設省の河川法の改正は、長良川河口堰の反対各会に寄るところが大きいと思います。「環境的に重要」というコンセプトと「対話」が、この100年来初めて加わりました。このことは、茨城や緒川の役に立ちましたか。
― この改正の影響はほとんどありませんでした。長良川の河口堰とか吉野川の第十堰とか自然の生態系を壊すということが市民運動として基本にあると思うんだけど、国はコンクリートで固めて魚などが上がれないようにしてしまう… それではマズイということで始まった運動なので、今までのように大きなダムのような堰をつくったりせずに、きちんと評価してゆくのは良いことだと思う。ただ国としてはやっぱり色々あるんでしょうね、ゼネコンの関係とかもあるんだろうしね。建設省(現国土交通省)がやるから、あんまり自然環境保護とか生態系とか頭にはないんだね。工事をやるこの水をどう利用しようか…ということしか頭にない。
・ 長良川の反対運動団体は、米国の議員の方などに会って研究している天野礼子さんとか、英語で発表されたり、HPもあります。
― そうですね。天野礼子さんは環境問題とかの活動されてますね。私は天野さんの本は読んでます。
 『ダムと日本』天野礼子 岩波書店
『ダムと日本』天野礼子 岩波書店・ 米国はダム建設を取り止めています。
― そう。もうつくらない。壊す方向にね。アメリカの場合も、昭和の初めに大恐慌があったよね。当時のルーズベルト大統領も公共事業を起こして、景気を上げようという方式で方々へダムをつくったわけですよ。けれど今になって考えてみれば、生態系は壊す自然環境の破壊で結局ダムは必要ないだろうという結果に至って、ダムを取り壊している。天野さんなんかは、そのような影響を受けているんじゃないかね。
政府の公正さの欠如は橋本知事(平成13年/2001年~)の村民への謝罪の手紙に同様に表れています。30年以上損害を与えたにもかかわらず、知事は賠償金については不可能だといい、疲れきった住民に対し、最低限の必要に叶う社会設備などの建設で埋め合わせようとします。
Q 17 - a この手紙と、戦い最後の期間にはどのような思い出がありますか。
小林 平成12年に正式に県の方で緒川ダムを中止することを発表しました。その時に起こった問題は、その33年間住民をいわば苦しめた、ダムを中止するならばその間住民に与えた精神的な苦痛や経済的な損失への補償をするべきだろう、という美和村と緒川村の地権者、住民団体からの声が出たんですよ。県の方へ申し入れもしたし話し合いのときもその問題は出したということで。その時県の方で世論アンケート調査をやったら「補償しろ」という声が圧倒的に多かったから、県でも困った。無視するわけにもいかないでしょ。県の内部でも「補償すべきだ」という意見もあったらしいけれど、最終的には県知事の判断だからね。橋本さんは、今の状況では補償はできないから、公共投資、いわゆる道路をつくる橋をかける、公民館を建てるとか、色んな整備をする、それで納得してください、ということだった。個人補償はいたしません、ということだった。
・ 個人補償を拒否する理由というのは何なんですか。
― 法的な根拠がないんだね。公共事業を途中でやめた場合に住民に補償するという法律がないんですよ。
・ ダムが完成してたらいいのですか。
― 完成してたら補償問題にならないからね。土地とか家屋の。だから完成してれば問題ない。中止になったからその問題がでてきた。
・ だからこそ、憲法第十三条の“自由と幸福追求の権利”が重要になると思います。生きるための基本的人権…。では、その当時の思い出に関しては…。
― 今だって、納得はしていませんよ……誰もね。緒川ダムが中止になった時に、鳥取県の三朝(みささ)の中部ダムという、ここと同じようなダムが中止になって、鳥取県は住民に対して補償をしている。『幻のダム…』の228ページに書いてあるんだけど、住宅への助成が300万円とか、利子補給制度が60万、高齢者向けのバリアフリー化住宅への助成が80万、ダム関係集落2地区に地域振興活動資金として5000万…。県では鳥取県までダム砂防課の職員を派遣して調査してきたんですよね。でも県知事の考えは変わらなかった。それで、なぜあんなに補償したかという理由は、金を出して住宅をつくっていかないと、その地帯がますます過疎になるので金を出しているという。これ理屈にならないんだけどね。言い訳みたいな理由なんだけど、とにかくそういう状況なんです。美和村の職員も鳥取に行って話を聞いて、だいぶショック受けたみたいだね。あちらでは手厚い保護をしているのに、こちらは何にもない。かなりショックだったみたい。(笑)ほとんど同じような条件のダムだったからね。
・ 三朝町長さんが自民党だったからとか。
― 鳥取の県知事も茨城の橋本知事も、元自治省の高級官僚なんです。でも鳥取県は革新派の知事なんだね。だからそれもある。知事の考え方の違いだよね。
・ 橋本知事は他の知事のように汚職知事でしょうか。
― 前の竹内知事が汚職で捕まってるから、そこら辺は警戒してやってる、いや、表には出ないでしょ。いや、やってないと思うよ。(笑)
・ 茨城県のインターネットサイトを見ると、非常にネオリベラリスム新自由主義で経済の規制緩和の県政とあります。産業部門の規制の圧力を緩和する、茨城への企業誘致なども推進している。
― こないだ県議会選挙があったけれど、その辺は言われていたでしょうね。無駄な公共事業、例えば常陸那珂港とか百里の飛行場の民間共用など批判はありました。
・ 飛行場をつくっているんですか。国内線、国際線?
― 小川町(現小美玉市)の百里基地は航空自衛隊専門だったんだけど、2、3年前から民間の発着もできるようにしようと工事をやってるんです。国内線のね。ただあそこへつくっても利用客はそんなにないんじゃないかという見通しなんです。県の方では需要はあると言うけれど一般から見ればそれには疑問があるから、反対も多いけれど、滑走路をもう一本増設している。でも成田は近いし、羽田はあるし、福島も近いし…。採算的には赤字なんじゃない。そして今度米軍再編で軍用機が飛んできてあそこで訓練する計画があるんですよ。
・ じゃ、騒音とか、大気汚染とか。沖縄や厚木みたいに。
― そう。騒音とか航空機事故とかの心配はある。住民は署名して反対運動しているんだけど国の方で強引に押し付けてきているから決着はどうなるか…。

”一坪運動”の反対闘争により「くの字」に曲がった百里基地の誘導路。
・ ところで日本には秘密収容所はありませんか。
― んー。それはないでしょう。(笑)
・ 隠れ核シェルターは。
― それもないでしょう。(爆笑)
・ でも日本は4000も島があって、ないと言うには無理がある。秘密刑務所くらいあるでしょう。
― アメリカの基地の中はわからないね。日本の目が届かないからね。
・ 治外法権ですからね。
― そうだね。あるかもしれないけどわからない。政府でもわからないでしょ。(笑)
・ 日本政府は米国に完全に操作されているかもしれないですね。
― そうそう。
世界ダム委員会会長で南アフリカの教育相カダー・アスマル教授は、2000年に「10億ドルのダムを造る必要はありません。その建造物が一番弱い人達のすべてを失わせるのなら…」と表明しています。「幻のダム…」は最初から最後までこの不安がよみがえってきます。 インドでも世界でもダム反対運動のパイオニアであるメダ・パットカーは、インドの大型ダムの50%が建設にこぎ着けていないし、生きる権利、存在する手段を持つ権利、部族コミュニティーの権利、聖域の権利である基本的人権をつねに侵している…といいます。
Q 18 - a 日本の大ダムは目的を果たしていますか。特に黒部ダム、奥只見ダム、黒又川ダムなど。
小林 今までできた発電ダムについては、かなり有効に働いていると思いますね。特に黒部ダムは観光の拠点になって、立山黒部アルペンルートとかの道路も人気ですよね。
![]() 《 八ッ場あしたの会 渡辺洋子氏より 》
《 八ッ場あしたの会 渡辺洋子氏より 》
緒川ダム予定地で反対運動をされていた小林さんが語っておられる地元の状況は、八ッ場の水没予定地の状況とよく似ています。成田闘争を見て、外部の運動家らが入る危険を感じ、地元の人々だけで闘うという戦術をとったことです。
外部は、自分達の都合で動きますから、農山村の人々が警戒するのも無理はありません。
けれども、閉鎖的になることで、全国のダム反対闘争が孤立し、行政側に押し切られていったのも事実です。今まで、ダム反対運動が成功してダムが止まった事例は殆どありません。
反対運動があって、ダムが止まった事例でも、先に行政側に財政上、政治上、ダムを中止したい理由があるのが普通だからです。
もし、外部の協力を仰いだとしても、やはり村内に混乱が起こり、ダム中止を勝ち取ることは難しかったでしょう。現在、八ッ場ダムでは、地元が補償交渉を終え、ダム推進に転じ、下流の都市住民がムダな公共事業に反対という立場で訴訟を起こしています。
かつてと立場は逆転しましたが、地方と都市との対立は深まるばかりです。
あしたの会(旧八ツ場ダムを考える会)では、この問題の克服を大きな目的としていますが、ダムを受け入れてしまった地元と外部とが関係をつくるのは補償の問題があり、容易ではありません。
八ッ場で今、ダムが止まっても、個別補償はムリとされています。世界ダム委員会の見解などから、何かよいお知恵があれば教えて下さい。
『八ッ場ダムの闘い』という本は、大変面白い本ですが、問題の多い本でもあります。
たいてい、この本を手にとる読者は、著者がダム反対運動の中心人物だったと思ってしまうのでは ないでしょうか。
萩原さんはダム条件付賛成派でした。八ッ場ダムの反対闘争はいまだに本当のことが書かれていません。
萩原さんは閉鎖的な水没予定地にあって、外部と連携することで有利な条件闘争を試みました。けれども、その外部とは、八ッ場ダムの最大の推進者、福田赳夫元総理でした。萩原さんは、福田さんと結ぶことで、反対期成同盟を追い詰め、ダム反対運動を終結させることに加担してしまいました。このような背景は本には書いてありませんが、念頭に入れて読まれると、より興味深いかと思います。
…… 萩原さんは失意のうちに亡くなられたのだと思います。
故郷を守りたいというだけの純朴な反対期成同盟の人々を愚かだと見下していた、そのご自分の驕りがダム推進者にとって思う壺だったことに気がついておられたかどうか、それはわかりません。…
(2007.1.29)
![]() 八ッ場ダムは疑問だらけ
八ッ場ダムは疑問だらけ
![]() 《 八ッ場ダム裁判 一都五県下流住民訴訟 》
《 八ッ場ダム裁判 一都五県下流住民訴訟 》
2007年1月30日、水戸地裁で第十回目の住民訴訟裁判がありました。 意見陳述「八ツ場ダム建設計画の中止を求めて」と「八ツ場ダム貯水池周辺の地すべりの危険性」についてでした。
次回は2007年4月24日、11h30~です。

意見陳述された野口さん(左)と主要メンバー塚越さん。

閉廷後、弁護士団の説明会と嶋津暉之さん、神原禮二さんたちとミーティング
・ 自然環境的にもそれはポジティブでしたか。
― ダムは環境破壊だから、いくら黒部の発電ダムっていっても。TVとかでよくやっている土砂がダム底に溜まって危険だとか。ただこれから完成する八ツ場ダムとかは、つくる意味がないんだよね。八ツ場ダムというのは、東京の水源の一つとして50年前に計画されたけれど、東京は今は水はいらないんだよね。東京の水は群馬のいくつかのダムの水を主体に使っていて、奥多摩湖の小河内ダムは予備の水で、よほど渇水がないと使わないんだけれど、小河内ダムの水は使ってないから。そういう渇水対策はできているので、現在の水の計算からいうと八ツ場ダムはほとんど必要ない。だから選挙のときも共産党あたりが八ツ場、湯西川は必要ないんだと、公共事業の金の無駄遣いだという指摘をしていたけれど、このダムのせいで県の負担金が増えたんですよね。八ツ場に払う茨城県の負担額が123億円の予定のところ倍の269億円になった。湯西川ダムへも213億円から258億円に増えた。
(一都五県の住民訴訟)

『八ツ場ダムは止まるか』 ― 首都圏最後の巨大ダム計画、八ッ場ダムを考える会編 岩波ブックレット
隈大二郎、嶋津暉之、まさのあつこ共著
ダム反対派、脱ダム理論。「…脱ダムの集大成といわれる八ッ場ダム問題への"道案内"…(八ッ場ダムを考える会HP、本の紹介より)」
 『八ツ場ダムの闘い』萩原好夫、1996年、岩波書店
『八ツ場ダムの闘い』萩原好夫、1996年、岩波書店
著者は、ダム条件付賛成派。八ッ場ダムの最大の推進者、福田赳夫元総理との交友にもかかわらず、激しい条件闘争を余儀なくされる。1999年没。
・ 八ツ場は2010年に完成予定ですね。
― できないでしょうね。まだ本体工事が始まってませんから。
- b 民営の開発事業会社の得る利益とはなんですか。
― ゼネコン、総合建設会社っていうのかな。工事をやる利益それは当然入るでしょうね。
・ ダム運営というのはどうなっているのですか。
― 運営は建設省(現国交省)。
・ 利水者を探すのも建設省(国交省)。
― 利水というのは、ダムを造る計画の段階で配分は決まってますから、新たに利水者を求めるということはしない。何県は何億トンを利用するとか… ダムができてからは探すことはしない。大きいダムは国で運営して、県営のダムは県の土木部が管理するということだね。運営というより、洪水の時、水量をどう調整するかどうかとか…。
・ 財政面の運営というのはどこがやるのですか。
― 結局、利水者の方から水道料を取りますよね。県の場合は企業局でやっているんだと思うんだけど、それが入ってくるお金。
・ ダムができると水道代が高くなるんですか、茨城が払う八ツ場のためのこの269億円という金額は高いですか、安いですか。
― ダムの建設費は水道料金に跳ね返る。この1トンの水を供給するのにいくらかかった、というのを計算する
・ 269億円を最初に払って、プラス毎月水代を払う
― そうです。ただダムの建設費の捻出というのは国の助成があって、利水を利用する県の払う工事費がある。水を利用する県が払う、ダムをつくる、そして今度は水道を引く。それらを計算すれば100円になるか200円になるか…いくらになるかでるわけよ。
・ ということは国の方では採算は合っているということ…。
― 水道料としてね。
・ 利潤は。儲けはなくていいわけですよね。
― 利潤はないけど、結局原価計算で水道料は決まるでしょ。それを集めればいいだけです。
儲けなくていい。儲けてたりしてね。(笑)簡単だもんね。でも文句でるよね。だから収支トントンでいいんだよね。
・ 国の水に関する財政状況というのはわかるのですか。すごい金額でしょうね。
― 調べればわかるだろうね。茨城でいえば、県南水道事務所、県中央、県西とか、6ブロック(4水系)に分けてやってますから、入る金、出る金で収支が合っている。
・ 茨城は国から水に関しての援助はあるのですか。
― ダムに関しては、国から工事費の2分の1の補助がでるんです。あとの2分の1は県の方で負担するという形になります。どうなんだろうなあ、補助金というのは来ていると思うよ。調べてみないとわからないけれど。
人口1億2700万の日本は、10億人のインドと同様、自家水・井戸・地下水の国です。55.6%の農耕可能面積は個々の井戸・取り水・地下水によって灌漑されていますが、2000年にはダムによる灌漑率は30%で、穀物生産のためには主要ではありません
- c 日本の家庭や農業経済にとって、自家水・井戸・地下水は期待できる要素になり得るものでしょうか。
― 水道事業が広がって、農家を含めた一般の家庭では水道水に頼る割合が年々高くなっているんです。井戸水は、飲み水としては検査すると不適になるんですよ。この辺はどこでも井戸持っているけれど、飲料水には無理だと。村の方で検査すると全部不適なんですね。なのでほとんど村の水道から生活用水をとっている。
・ 水道の水といっても、緒川地区の場合は川の伏流水だから、井戸といえるのではないですか。
― 緒川の伏流水をとって、塩素で消毒してある。それを配水しているわけです。
・ 個々の井戸はまだまだ使用されていると思うのですけれど。
― 旧緒川村は、水道の普及率はこの辺では98%で一番高いんですよ。まだ従来からの井戸を使っている家もあります。お風呂に使うとか庭に撒くとか、私のところでもそうです。
・ 井戸の水は昔に比べて汚くなったのですか。飲めないくらい…。
― いや、飲めますよ。井戸水を飲んで、下痢するとかお腹をこわすとかはないんです。今は検査が精密になってるから、大腸菌がでたり…。
・ では、水質が悪くなったということではないんですか。
― ないんですよ。昔から条件は変わってないからね、ここら辺は。でも昔は検査とかはなかったから、実際飲んで大丈夫だったわけだから。 フィルターを使えば十分きれいになるけれど、殺菌まではできないんだね。個人では設備もないし塩素消毒なんてできないでしょ
・ ここの井戸は、緒川に近いから緒川の伏流水ですか。
― いや、山の方から流れてくる地下水で、水脈は違うみたいですよ。水道が入る前はずっと昔から井戸を使ってたわけですよ。車井戸、滑車で縄で汲み上げる。今は電気ポンプ。
- d ダムの代替案があるとしたらなんでしょうか。
― 結局は、水というのは山から流れてくる。森林を整備して”緑のダム―グリーンダム”を育てた方が、わたしは良いと思う。山を切るのではなく、杉山がびっしり生えているところを間伐して、山を整備して水が沁みさせるようなやり方。自然破壊してダムをつくったりするより、この代替案グリーンダムが良いと思おう。
- e 日本のダム建設反対運動から得られる教訓はなんでしょうか。
― ダムというのは、地元の住民が望まないのにやってくる、という傾向があるよね。住民の意見をよく検討して、反対ならばつくらない、賛成ならつくる…というように住民を尊重してやることが重要だということだね。具体的にいうと住民投票ということになるでしょうね。
・ フランスでは、市民提案による代替案意思決定投票といいますが、すべての市民社会の活動を決めていく時に投票を義務づけるということです。新しい議会制度を検討している人達がいて、憲法改正の構想の一つなのです。例えばエチエンヌ・シュアールという活動家は、選挙で議員を選ばずにくじ引きで議員を選ぶ投票の無い制度を提案しています。
― それは問題あるでしょうね。議会制というのは同じような考えの人がまとまって代表を出し議会に送るというシステムでしょ。抽選とかではどういう考えを持っている人が出るかわからない。議会の形を成さないと思うんですよね。極端な話、主義主張のない人が当たってしまうかもしれない。
・ それが目的です。政党からの派遣を避ける、自立運営です。裁判員制度のようなものです。政治性を無くすために無作為に選ぶのです。
― 裁判の場合は、裁判長や裁判官がいて、検事、弁護士そして陪審員がいる。プロがいて素人が判断する仕組みがある。でも議会というのはテクノクラートというか専門家が集まって協議しないと成り立たない。
・ 単純に私が言いたいのは、公益に尽くすために政党、政治性は必要ないということなんですが。
― それはちょっと疑問がある。
・ 問題なのは、自立運営組織の中では、従来の政治形態は放棄されるべく、そのためにアマルティア・センのコンセプトを何度も引き出すのですが、政治組織と共同体運営は倫理的に相容れない、数のせいで。数というのは、人数=大多数です。倫理は“多数”の敵なのです。我々が多数になればなるほど倫理が減ります。一人に対してひとつの倫理しか成り立ちません。まず最初に、このような政治の概念があるのです。
― こういう小さな村を例えにすると、村の予算とか色々決める時に村人が全員集まって相談するのが一番良い。でも4000人も5000人も集まるわけにはいかない。だから代表者を出す。これは村でも国でも同じだけど、議員を選ぶ、即ち、同じ考えを持っている人、人格が優れている人を皆見て、投票して選ぶことで議会ができるわけで、そこで初めて機能するんじゃないの。それは理想的な形だと思うんだけど、今の国会見ていると必ずしもそういう人が選ばれているとは思えないけどね。
・ けれども先ほどあったように経済的有用の村長派14対反対派2、というような緒川村の議会で、意見が反映された民主主義の代表者システムというよりも、なにか他のシステムが作用していたのではないですか。
― 民主主義の基本は多数決の原理というのがある。そのアンチテーゼで少数意見を尊重するというのがある。それが倫理的に見て、相俟って運営されればそれほど間違った方向に行かないと思う。
Q 19 権利や収入、福祉、公正、自由が有効な市民生活がどんどん減少する中で、知事たちは県民の精神反応をただ見ているだけに留まり、社会組織を上辺だけで判断します。人間理解に欠くアプローチをネオリベラリスム精神の染み込んだ地域共同体管理システムに加えるのです。そしてその精神も、また人や組織の表面的なアプローチを持つにとどまっています。数々の証人の視点によると、金を追いかけたり、毎月末には従業員に給料を払うことでけりをつけるような財政的利益を追う、議員自らが、まさに企業の指揮者のようになってしまっていることです。
最終的には、小売店でも金融機関でもないはずの役所が、GDPの41%(2006年)という慢性の負債を抱えていることです。
わたしたちの住む(合併で緒川村と美和村の含まれた)常陸大宮市は270億円という記録的負債があり(緒川ダムの事業費260億円とだいたい同じです)、2006年現在、市民一人当たり64万円の借金になります。
小林 これは役所の放漫経営ですよね。主には、必要もないのに大きな建物を造ったりしたことで借金が増えてしまったということでしょうね。贅沢な市庁舎とかロゼホールとか、福祉センター…。
緒川地区でも総合センター(図書館、コンサートホール、イベント室、会議室、歯科医院など)とか総合体育グランドなどの大きな設備をつくる、というのは、住民の意見をあんまり聞いてないということだよね。もう一つは計画性がないということが言えると思う。常陸大宮市として合併するならば、あのような大きな建物は必要なかった。あれをつくった時には緒川村は単独でやってゆく方向だったから合併ということは視野に入ってなかった。
・ あれはダム関連の…ですか。
― 関係ない。もう一つのグランド(運動公園)。あれは、総合センター建てたところがグランドだったから、現在の場所を新たに設けてつくった。今から考えれば、合併したら必要のないものをつくってしまったわけですよ、あのような大きなグランドは必要ない。
・ 資本主義は健全な財政運営と相反するところがある、と以前に小林さんがおっしゃいました。
― いわゆる無計画性、役所の放漫経営、借金が増えることに対する罪悪感みたいなのはないんだよね。借金は後々の世代に送られてしまうわけだから。現在だけなんなく過ごせれば…という思いが役所の幹部にはあるんじゃないかと思うんだよね。
・ 道具化している。
― そうそう。事業が失敗だと思っても、一度始まってしまうと中止したり引き返したりしない役所の体質があるんですよね。よく県の仕事で例に挙げられるのは、常陸那珂港。一日に2隻くらいしか船が入らない港に何千億という金を投資しているでしょう。それをやめない。事業として動き出したから決断がつかないという、役所の体質的なものだろうね。あれは役所の典型的な無駄遣いなんです。あそこは湾になっていない太平洋の波をもろに受ける港なので、長い防波堤をつくらなければいけないので、ケーソンといって五階建てくらいのコンクリートの塊を沈めていく。そのケーソンが一個10億円くらいする。それをドボンドボンと沈めて防波堤にする。一旦事業が始まってしまうと止めない戻れない、検討しないのは知事のいい加減なところだよね。
あなた方のダム反対は、国民の生活に不可欠なものが何であるかを、人々の個々の事情の多様さを把握できない無能な政治を象徴しています。同時に、知事らは信頼できる良識の指針ではないこともわかります。
この間違ったシステムは、老齢者や困窮者に対する無関心さを育ててゆきます。常陸大宮市に合併された山方方面に行く道で、沿道の草刈り作業で市から雇われた方達に混じって80歳ほどの女性が働いているのを見て驚きました。この悪システムへの依存は、危機や病気や老化といった、食・衣・住・移動・治療・保護・社会伝達や交代価値を生む基本になる可能な能力を持とうとする民の障害になります。
インドの経済学者アマルティヤ・センの倫理のベースの一つがそれです。緒川村と美和村の村民が受けなければならなくなった「水のストレス」という社会歴史的事件の緯糸です。
同様の考え方で他の動きを見てみると、例えばメキシコのラ・パロタのパパガヨ川のダム計画の反対運動の基礎となっています。2006年3月時点で、18村の水没と25000人の移転が予定されています。このダムは、主にリゾート地・アカプルコに水道を供給するためなのです。住民のバリケードが作られています。石や農具、大刀で戦っているのです。
・ 老齢者とか貧困者の問題は。
― 今、道路の草刈りとか整備は、市のほうから建設会社に発注してやってもらっている。建設業自体も若い人がなかなか入らなくて従業員が老齢化していますから、おばあさんも頼むということになっちゃうんじゃないかな。
・ でもどう見てもあの女性は75才以上でした。まるで社会の決まりがなくなってしまったような感じでした。
― 決まりはあることはあるんだけれど、弱者というか、最近は、所得格差が開いてきているということと、生活保護を受けている人も極端に増えているんだよね。被保護世帯も100万越えているというんだよね。国の方では生活保護を減らそうということで、このあいだニュースでやっていたけれど、母子家庭には一般の生活保護の他に母子加算といって月に2万か3万もらっていたんですよ。あとは老齢加算もあったんだけれど、今度は母子加算も老齢加算も削ろうという方針を出しているんですよね。
・ 田舎は過疎化していて税金も減っている、市の運営はピラミッド型になってしまって、例えば北海道の倶知安町の伊藤町長は「町として企業の経営者のように金稼ぎ(金を追う)をせざるを得ない」といっています。目先の大金儲けの機会に食らいついていく、先の結果がどうであれ。これはどうしたことでしょうか。民間経営を余儀なくされた民主主義ではないですか。しかし、教師へ払う給料は削減、行政職員も削減…人々はただの道具ではありませんか。
― この前も言いましたけれど、新自由主義―ネオリベラリスムというのは、効率第一でお金を儲けることに最大の価値観を置くということでしょ、経済合理主義だからね。そういう考え方を政治的に進められると、所得の格差が開いて、お金を持っていない人が増えた底辺のピラミッド型の社会構造になる、という心配があると思う。
・ 資本主義下であるのに、金の役割、金とはなんだろうという思考はされていません。一日に2ドル以下で生活する人は地球上に45億人にいます。このことについてどう思いますか。
― 貧困層ですね。どうなんでしょう、その国の所得が低いのか、後進国なのか…。
・ 彼らは乞食同然、死を待っている状態だと世界保健機関 WHO はいっています。
― 日本でも1980年代の頃は、総中流、ミドルクラスだといわれていたんですが、90何年かにバブルがはじけた後、所得格差が広がってきた。今はだから格差社会といわれているんです。
Q 20 ホワイトカラー(経営幹部や政治家など)による犯罪、組織化された強盗やちょっとしたそこらの犯罪行為は単なる偶然の果実だとは思いません。2004年の日本の警察の発表では、61300人のやくざがおり、日本の犯罪の70%が彼らの手によるところだそうです。私たちは、ビジネス犯罪や地方または中央政治における組織立った犯罪の力を知っています。小泉前総理大臣は、「自分の選挙区のボスの名を無視する国会議員は一人もいないでしょう…」と”不良債権”に関連する組織犯罪に言及しています。
他には、返済不可能な銀行貸付け”不良債権”の総額は2兆ドルに上りますし、8000億ドルの返済不可能な借金が、民間企業の50%に及ぶやくざ関連のダミー(幽霊)会社に公共のなんらかの力によって保証されています。
小林 ホワイトカラー犯罪がなぜ起こるかというのは、その犯罪を起こす人の資質によると思う。今の土建政治的な体質を利用して自分の利権を謀ろうということだと思うんだけれど、一つは、法律の抜け道というか非常にカムフラージュして犯罪が行われている。
・ 政治や法律のシステムが汚職や犯罪をしやすい方向にあるのでは。
― システムが犯罪に向かわせるのではなくて、そのシステムを利用してお金儲けをしようとする政治家の性質、性格が問題だと思います。たとえ誘惑があっても負けない、というようなものがない。
・ 先日、”資本主義と健全財政の行政運営は不適合”とおっしゃってました。
― 行政のシステムというのは法的に見ると、悪いことができないシステムになっているんです。ただ、資本主義の論理というのは利潤の追究でしょ。ホワイトカラー犯罪というのは、その行政システムの隙間を縫って悪いことをすること。
・ 日本においては「正統な犯罪権力の勝利」といえませんか。例えば、シシリア・マフィア社会研究者のウンベルト・サンティーノは「政治機関、市場、権利へ浸透したマフィアの勝利」と書き留めています。
― 日本の公的な立場に立つもの、例えば議員とか知事とか国会議員とかは選挙によって上がってくる。選挙があると、企業、業者に世話になるわけですよ。献金してもらったり、従業員に選挙運動してもらったり。選挙を通じて特定の業界と癒着、関係ができる。例えば県とかで色々発注するときに世話になった企業へ有利に仕事を頼む。県知事などは権限が強い、第一、職員を自由に動かす人事権があるし、予算を編成する権限、そのお金を使う権限があるから、やろうと思えば自由にできるものすごい権力があるんです。いわゆる県知事の命令―この業者にやらせたいとかを「天の声」というんだよ。だから知事の言う事聞かない、たまに骨っぽいのがいる、そういう職員は左遷というか、他の部署に移して、言う事を聞く職員を自分の周りに置いたり自由にしているんです。
・ 不良債権については。
― 不良債権は、バブル期に銀行が不動産を中心に土地を担保に貸した。バブル後に地価が下がったから、借りたほうでも返せなくなってしまう。そういう理由で不良債権が大きくなった。地上げ屋さんとかいろいろ騒がれた時代があったでしょ、あの時は、土地を担保にして金をどんどん貸したんですよね。
・ 不良債権というのは、主に土地ですか。
― 土地と株、ゴルフの会員権。これがバブルの成長株だった。土地を持っていれば損しない、株を持っていれば必ず上がる。ゴルフの会員権も必ず上がるということだったんだけれど、バブルがはじけてみんなダメになっちゃったでしょ。だから不良債権がどんどん出てしまったんです。例えば、ここにロックヒルっていうゴルフクラブ、バブルの最盛期に造成したんだけど、最初、会員権は2000万円くらいした。それが500万になり、300万になり…。どんどん下がった
それから、マフィアのことについてだけれど、ここらへんにいる暴力団とかの組織とはちょっと違う。不良債権の処理なんかではやくざの絡みはあったようですが、銀行ではダミー会社などを通じて暴力団的な人間を使ったり、地上げ屋の役をやったのは主にやくざなんですよね。
・ 日本では犯罪組織は発達していますか、それとも…。
― 暴力団に対しては警察の取り締まりが厳しいから、それほど悪どい犯罪はやらないよ。
・ 茨城県では2004年、43件の暴力団関係が検挙されています。
― 茨城は少ない方じゃないんですか。西日本の方が多いのかもしれませんが、少人数ですがいますよね。ただ日本では暴力団は住みづらいのではないですか。一般の人や自治体は、暴力団を排除するでしょ。
・ オウム真理教のもそうだけれど、暴力団追放とかの看板を目にします。
― 温泉に行くと「入れ墨のかたお断り」ってあるでしょ。
北海道の地方自治権と平成の合併反対にかんするインタビューを、衆議院日本国憲法に関する憲法調査特別委員で衆議院議員(前北海道ニセコ町長/ 民主党)の 逢坂誠二氏にした時に、調査特別委員会委員長の自民党・中山太郎氏により提出された報告書は、扇動的傾向があるのではないかと私は思いました。中山太郎氏は、社会や人々のオーガニゼーションに関して、科学、医療、バイオエシックス(生命倫理)やインターネットの進歩効率を目的にした憲法(公正正義の可能力であるはずの)に盲目的な信頼を置いています。
彼は、憲法とは人間の基本的人権と利益を保護するという基本に則っていると断言します。しかし、どうでしょう、ダム反対運動の歴史やその法律がまるで正反対であることを証明しています。実際には、日本においては、憲法上の権利や私有財産を守ることは、国や大企業の権力の前では到底立ち向かえないのです。
Q 21 - a 日本では、人々は法律を恐それていますか。
― 一般的にいえば、嫌いということではないと思うんです。法律は基本的人権を守るものです。日常生活においては「法律」とかは頭にないから、普通に生活していれば法律は必要ないし、犯罪したとか犯罪に巻き込まれた場合当然必要になるのではないでしょうか。
・ 中山太郎氏は憲法に多大な重要性を置いていますが、その調査特別委員会の報告書を見てとても偽善的だと思いました。対ダムの訴訟などは良い例です。個人は訴訟に負け、法律はいつも企業を保護するようにできているようで、企業の権力を思い知らされます。訴訟などの法的に社会運動から鑑みて、科学や医療などは経済要素として配慮されているようです。
― 今は日本の政治そのものが転換点にあるんですよね。今までは日本が戦争に負けた事によって、戦前の強圧的な国家主義的な法律が廃止されて民主主義的な法律になった。憲法はじめ教育基本法なんかもね。それが戦後60年経って、戦前の価値観に近い法律に変えられようとしている。例えばこのあいだ決まった教育基本法。今までは個人の能力、人格を完成させるのが教育の目的だったんですよね。今度は、国とか郷土を愛するとか、公的なもの「国」「国家」を上に置くような精神、今までは「私、個人」が重要だったのに、逆転するような法律改正なんですよね。その他にも今問題になっている、労働法。一週間の決まっていた労働時間を撤廃しようとする動きがあるんですよね。だからここにあるように大企業の利益に合うような法律改正がどんどん進んでいる。
・ 他の言い方で質問すると、例えば、自由主義の文脈の中で議員とか市長とか知事など選挙によって選ばれる人たちが、電通のようなコミュニケーション広告会社が市場や有権者や市民をコントロールするために作成する報告書を元にリアクションするようになったということです。
― それは、クリスチャンはよく見ているね、日本の社会を。
・ 中山太郎氏の報告書を見て、心配になった点は「国民の心理操作はしてない」と断言していることです。
― 中山太郎さんは自民党の憲法調査会の会長なんですよね。今の憲法というのは、平和と民主主義と基本的人権の三本柱で持っている。それを変えようとするわけですから、彼の言う「基本的人権と個人の利益を保護する」というのは偽善的になるし、本音と建前が違うような感じですね。だから、クリスチャンが言う「憲法上の権利や私有財産を守ることは、国や大企業の権力の前では無力」という方が正しいよね。
・ 彼は、自分は科学や技術、医学、生命倫理、IT的効果に耳を傾けているといっていますが、これらが形成する社会というのは実は”電通”が作り上げたものではないでしょうか。このような”事実”を担った憲法が、電通の作り上げた「個人の要求という効果」の閉じた輪の中で、その効果に則って作られるということです。自分が自分の意見を聞いているようなものです。
― 国とか大企業の利益を擁護していく、そのためには国民の民主的な権利を抑圧しないと国家の権力は守れないというのもあるでしょう。
・ 中山太郎さんは、お医者さんの出で、自分は苦しみが何であるかよく知っていると言います。学識経験者による科学的経済的な裏付けをし、企業に有利な憲法をつくっているのです
― 憲法改正の狙いというのは、平和主義とか民主主義と基本的人権を、それをある程度権力の方で自由にできるように改正するということだと思うんです。例えば、今の憲法では戦争はできない、本当は海外派遣もできないんだけれど、自民党はへ理屈をつけて海外にも出している。憲法を条文通りに解釈すればできないこと。そういう風に政府の判断で自由にできるように、枠を憲法から取ろうということ。
![]() 《 07年2月14日 河川整備基本方針・河川整備計画策定問題に関するシンポジウム 》
《 07年2月14日 河川整備基本方針・河川整備計画策定問題に関するシンポジウム 》

![]() 《 川辺川利水「ダムに依存せず」、農水省が通知…文書で回答 》
《 川辺川利水「ダムに依存せず」、農水省が通知…文書で回答 》
2007年1月31日 読売
・ 個人が企業に対して訴訟を起こすと、ほとんどの場合が敗訴です。小林さんらのダムの話にまったく当てはまると思いませんか。
― 例えばダムで訴訟をやって勝った例もあるんですよね、川辺川ダムとか(川辺川ダム利水訴訟
2003年福岡高等裁判所)。あれは下流の住民が工事差し止めをした。

『川辺川ダムはいらん!PART2』 ダムがもたらす環境破壊、川辺川ダム問題ブックレット編集委員会著
法学政治学の北村一郎教授は、「日本では法律は嫌われている」という法律研究家の野田良之先生の保守的な言葉を挙げて、法律の原則が個々に湧き出させる悲壮的な精神状態や心理反応を研究することで、日本人の法律家たちは、法律に対する日本人の特殊な関わり方をより理解できるのではないか、と言っています。
・ フランスで教えている北村教授も言っているように”基本的人権の”勝訴はあまり見受けられません。
― 法律は、その時の政治を支配している人の論理だし、裁判所自体がそういう政府に使われているわけだから。日本は、立法と行政と司法の三権分立で対等に成り立っているけれど、この司法、裁判制度だけは、政府に従属しているね。だから住民訴訟なんかは、最初の地方裁判所では勝っても高等裁判所、最高裁いくとほとんど負けてますよね。やっぱり国の論理が高等裁判所、最高裁判所に影響しているんですよ。最高裁判所の判事は、政府が任命するんだからね。裁判官の国民審査はあるけど、あれは形骸というか形だけだよね。やはり政府に人事権を握られてしまうとね。
・ 最高裁の人事替えは珍しいと聞いています。
― 人権派と呼ばれるような判事さんはあんまりいないんだよね。政府の言う事をよく聞くような裁判官が最高裁判所の裁判官になるから、結局全く独立した司法制度というのはあり得ないね。この制度の中ではね。
・ 野田先生と北村先生は、法と日本人の関係に関する精神分析的研究をしています。彼が心配する要素とは、日本人が法律に言及する時または法的なことに関わる時、悲壮的な精神的リアクションが現れるということです。これらの日本やフランスの研究者の目的は、その時代の法心理に合った法律や憲法を探し出すことです。そして「国体」としての憲法をつくる事です。つまり天皇にとって代わるところの法律です。
― 戦前の憲法、法律というのはいわゆる天皇制、天皇というのは国の体制なんですよね。国体を守るような方向で全ての法律ができあがった。家族制度にしても、長男しか相続権がない。天皇だってそうでしょう。憲法の理念というのはそのような方向だったんだけど、戦後は違って、天皇は飾り物。民衆の民主主義で、民衆の権利、基本的人権とかを上に持ってきた。それを今変えようとしている。それは面白くない、っていうことで。誰が面白くないかというと、大企業とか大金持ちとかだね。一般の民衆は、今の憲法が良いと認識していると思う。
・ 彼らは法律を変えるだけにとどまらず、法の心理を変えようとしています。
― 結局、国家が一人一人の心の中まで入って来れる。あの愛国心の問題なんかもそうでしょ。だからそういうふうに国が民衆を支配しやすいような国家体制をつくるための憲法を狙っているんですよね。
・ だから研究者などが、市場や企業、有権者に受け入れられる、彼らに検閲などされるわけがないような憲法や法律をつくろうとしているのです。
― それほどではないかもしれないけれど、なるべく批判的な意見が出せないような雰囲気とか空気をつくっている。
・ 私が中山さんの報告書を見て心配になったのはその点です。
― でも、そういう風な雰囲気をつくろうとしてもなかなかできないけれどもね。なぜなら、皆自由な意見を持って自由に意見を発表する、言論の自由や出版の自由が保証されているので、政府でやろうとしても、わたしはできないと思うよ。
・ それはそうかもしれないけれど「自分の庭の外には自分の自由はない」と私が解釈するところのヴォルテールの言葉があります。
― そうではないでしょう。
・ 与党はお金があって、野党はない、という現象はどう説明できるのですか。
― 政府与党というのは財界からもお金が上がってくる。だけどお金で、国民全体の心を支配する事はできないからね。
・ 心までは支配できない…? でも、電通はできています。靖国も、安倍晋三もやろうとしてます。
― つまり世論を形成してしまう。TVとかメディアを支配して…それは可能だよね。
・ フランスでは言論の自由はとても限界があります。自分の庭では自由に主張できても、意見の自由の影響レベルになるととても時間がかかります。
― フランスでもそうですか。じゃ日本と同じだね。(笑)フランスはもっと自由な国なんじゃないの。
・ ノン、ノン、ノン!全然。
― ノンけ。
・ 国家が民衆上に存在する民主的オプションに参加するつもりはありません。国家は私にとって友(ami)ではなく敵(ennemi)なのです。先祖、伝統というシステムのなかで儀式を執り行うことにおいて、個人の自由がないようなものです。昔のシステムと現在のシステムを比べて、新しいシステムは昔同様、むしろもっと指導管理的です。
― わたしはそんな風には見ないんだよね。人間の歴史というのは何百万年という昔からあったでしょ。人間の生きる権利とかは貴族とか王とかを除いて、一般の人間は虫けらみたいなもので食うや食わずでいたわけでしょ。例えばフランス革命なんかだと、それがひっくりかえって、皆平等だとかなる。(そのような過程を経て)ずうっとレベルは上がってきていると思うんです。
・ 進歩はあったかもしれないけれど、それは人間的なレベルではなくて、制度の進歩だといえると思います。
― 国というのは、元々、民衆を押さえつけるけれど、歴史が進んでゆくと、民衆の力も強くなる。その責め合いなんだよね。国は押さえつける、民衆はいやだという。今の日本がそういう状態なんだね。
・ 例えばここ50年来、フランスでは、政治家の姿勢は変わることなく、その代わり法律が変わっています。
― フランスのことはわからないけど、私はそうは思わないんだよね。一人一人の個人の力や能力、言論の力とかは延びていると思うんだ。
・ エリートは自らの人生を変えることができます。
― 日本のエリートは東京大学で、その連中というのは国家の組織の中へ入るんだよね。他は民衆を構成するメンバーで、支配される側。このような体制はフランスも日本も同じだと思うんですよね。ただフランスは民主主義の伝統が長いから、日本の方が政治体制としては遅れている。
・ 日本の民主主義は明治から始まっているのではないですか。200年前から。
― 明治は民主主義じゃない。日本の民主主義は戦後(第二次世界大戦後)から。
・ フランスでも革命の後、ナポレオン統治下では民主的ではなかった。法典をつくったのも民衆を統治するためで、王制、ドイツ、ロシアなど封建に対する民法典の帝国を樹立した。これは市民社会の自由権を使ったクーデターだったのです。
― ナポレオン法典というのは、彼の王制を強いた、国民を規制するためのものだから、民主的ではないね。
・ フランスでは近代民主国家は1870年を待たなければならなかったのですから。
今でも労働者階級の10%しか大学に進学できない。残り90%の大学一年生はブルジョワ階級出身です。“平等や友愛、公正”でいえば、知識を享受することを許されていないということです。
― ちょっと話題から逸れるかもしれないけれど、最近日本では格差社会が広がりつつある、金持ちはどんどんお金を持ち、貧乏人はどんどん貧困になるという形。上流階級はもう固定してしまった。高所得、高学歴。今は高所得じゃないと大学に入れられませんから。
- b 日本での法律に対する恐怖や抑圧は、人権の非認識や権力者やビジネス部門の犯罪の源泉となってしまっている…と思いますか。
― 犯罪の源泉とまではいえないと思うんだよね。
- c 小林さんは、法律は好きですか、そして法律とはあなたにとって何ですか。日本では法律は国民を保護していますか。
― 今はそうはいえなくなってきたね。保護しなくなりつつあるね。
・ “人権”を人々は嫌いですか。
―人権尊重はスローガンとして出ています。好きでしょう。
・ イラク戦争に関して、小泉政権への違憲訴訟は。
― いや、まだ起こしてないでしょう。
・ 私は京都で違憲訴訟を起こしている日本のグループを応援しています。憲法違反の犯罪者ということです。(現在12グループが訴訟中)
― ああ、そうですか。
・ 小林さんは“権利”も好きですか。
― 私は法律が自分が生きる権利を守っているという意識を持っている。
- d 憲法とはどのような役を演じるべきでしょうか。
― 国民の生活権利を守るという役目がある。今の日本の憲法は、大きな戦争をやった後に生まれた憲法なので、平和主義、それから戦前の反省から生まれた民主主義、人民の権利を保障する人権擁護、これが三本柱の憲法なんですよ。司法、立法、行政が三権分立で、お互いにこの憲法を守っていこうという体制がつくられたのね。ただ随分前からだけど、この憲法を、解釈憲法で例えば「戦争放棄の条項」があって、陸海軍の軍事力は持ちません、というのがあるにもかかわらず、自衛隊をつくる、軍事費はアメリカに次いで世界二位で、憲法の精神とは全く違った方向に進んでいるわけなんですよ。我々は、憲法を守るという立場だから改正にはノーと言っているんだけど、力不足で、それを止められないということでしょ。
- e 何か公正な権力であったり、規正する影響力が、現在の憲法の中に認められますか
― 今の憲法は理想的な憲法なんだわね。戦争をやらないとかね。昔、ものすごい戦争をやってしまったわけですよね、世界中を敵に回して日本とイタリアとドイツの三国同盟。ドイツというのはご存知のようにヒトラーの独裁国家で、日本は軍閥という軍隊の独裁国家、イタリアはムソリーニのファシズムの独裁三国家が世界を相手に戦争をやったという経験から新しい憲法というのはできたわけなんですよね。だから当然平和だし民主的で独裁は排除されている、人権は尊重するという、この憲法は、世界中の憲法を見て最も理想的な憲法じゃないかと思っているんだよね。国家権力が戦争へ暴走するのを規制する、抑える憲法ではないかと思う。
・ 安倍総理の憲法改正をどう思われますか。
― 去年自民党が改正草案を発表したんだけれど、具体的には五年後、五年以内かな、にやりたいと安倍さんは公約として言っているんだけど、この草案は、今の憲法からすると“アンチ”なんですよね。結局、軍隊は持つ公共や福祉の名目にして人権を押さえつけるという。私はもちろん反対なんですけれど。
- g 日本のための最良の憲法とは、どんなものでしょう。
― 私の考え方からすると、今の憲法でしょうね。
・ 「天皇」が入っていても…。
― あれは、まあ、将来的にはね、削除されるべきなんでしょうけれど…。今の段階でいえば、憲法が掲げている理念は最高だと思う。
小林さんは『万民救の旗のもとに』と題された史実の本を出されました。この本は私たちの村、茨城の小瀬の農民一揆について書かれています。小林さんの曾曾祖父や農民たちは、明治天皇下1873年、大久保政権の発した地租改正による厳しい税金の取り立てにもの申します。彼らは竹槍や農具で、時には猟銃で、不公正に対して戦います。
Q 22 この本のタイトルについて説明していただけますか。
― 「万民救」つまり万民を救う。地租改正の重い税金から農民を解放するという狙いがこの農民一揆にはあったわけね。この時の大義名分、スローガンが「万民救」だったんですよ。その旗のもとに結集したからなんです。旗というよりは”のぼり”の長いもの。それを掲げて県庁に押しかけよう、ということだった。


左:ミニチュア万民救旗。右:農民が掲げたのぼりには“万民救”の文字があったという。『万民救の旗のもとに』表紙装画“那珂郡農民一揆絵画”(茨城県立歴史館所蔵)
・ 当時の社会経済状況と政府軍はどのようになっていましたか。
― 徳川の封建時代から明治維新によって政府が移る過程だったんです。明治政府をつくるのには財政を確保しなくてはならないので、土地からあげる税金で賄おうとして地租を改正した。封建時代は、年貢、米なら米で納めたんです。地租改正後はそれを現金で納める。いわゆる近代的な租税制度ですよね。フランスだと革命があって王制から共和制に移ったような感じですけど、日本の場合はちょっと違う。明治維新では天皇が残り貴族などが残ったから、ブルジョワ革命ではないけれど…。明治政府によって新しい軍隊をつくる前は、封建領主が持っていた武士だった。明治が近代的な軍隊をつくるにあたって、地租改正の明治六年と同じ年に徴兵制をひくわけです。男子が二十歳の時に兵隊検査をするんです。身体検査をして、体格の良い者をくじ引きで必要なだけ採った。
・ 江戸時代は徴兵はなかったですね。
― 武士が戦った。農民が徴兵されて戦うことはなかった。明治になって農民だろうが士族だろうが全員が対象になって、平時は31680人、戦時は46350人を確保した。東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本の6ヶ所に軍隊を、鎮台といって国の方で司令部を置いた。江戸時代の侍が明治になって失業するわけ。その人達が新しい軍隊の幹部になるわけだよね。主に徴兵で集まった兵隊は農民の出だよね。
・ なぜこのような戦いがあり、どのくらい続いて、だれが勝ったのでしょうか。
― 地租改正の重い税金に対する反対運動。
・ 大久保政権… 内務大臣ですね。
― この人が実質的には一番力があったんでしょうね。あの時は三条実美という太政大臣がいるんですが、公家の出身だからそれほど力がない。地租改正を進めたのは内務卿で、その中に地租改正事務局をつくる。大久保政権という程ではないんだけど、最高実力者の大久保利通というのが正確かもしれない。
長い目で見ると、地租改正の法律が公布されてから、ずうっと、農民と政府の土地の検挙争いはあったんですよ。一揆まではいかなくても、小競り合いというか小さな争いはあった。小瀬一揆の明治9年に限っていえば、農民が動き出すのが4月から、負ける12月10日まで。実際に一揆という形をとったのは12月6日から5日間、県の役人と武力衝突したということです。表面的には国が勝った、農民隊は敗北。結局は、税金をまけてくれという闘争でしょ。戦には負けたけれど、税金は下がったんです。だから100%ではなかったけれど農民の要求が通ったわけだ。
― 一揆に話を戻すと、死者もでました。戦死された方と処刑された方。県の方から先申しますと、警部1名死亡、巡査3名死亡、重傷が5名、軽症が2名。以上が県側の損害。農民側は死亡7名、処刑3名で、明治の初めだから死刑にいくつか段階があって、一揆の首謀者1名は斬罪、その他2名は絞罪。
・ 首謀者が打ち首ってことは、その方が辛いから…。
― 死に方としては楽なんじゃないの。いや、そんなこと言っても殺されたわけじゃないからわからないけど。刀でスパッと斬るわけだから。話は脱線するかもしれないけれど、昔は首切り役人ってのがいたんですよ。罪人の首を斬る専門家が。フランスのギロチンは殺される方としては楽だと思うよ。パーンとね。
・ もし小林さんがこの時代に生きていたら、きっとリーダーでしたね。じゃ、打ち首ですね。
― だろうね。(笑)
・ 小林さんの曾曾祖父の方はどうだったのですか。
― 絞罪。
・ 2人のうちの1人のサブリーダー。
― 親方ではないけれど、幹部だね。
・ 小林さんは、その話を子供の頃から知っていましたか。
― 聞いていたね。でも具体的には大人になってから聞いた。色々な文章が出てきて分かるようになってから。でもおふくろから聞いたね。親父はしゃべんねんだな。嫌だったみたい。あんまり良いことじゃないからなあ。今は義民とかいってもてはやされているけれど、以前は罪人じゃないですか。あまり名誉なことではないから話すの嫌だったんじゃないかな。
話を戻すと、懲役を受けた方が26名、罰金刑が1064名(資料により1060から1070の間)。
 緒川総合センター駐車場横にある義民顕彰の碑。
緒川総合センター駐車場横にある義民顕彰の碑。

”…一揆に参加した農民の孫にあたる小森けんという女性が、犠牲者を祀った「義民堂」”。警官4名を含む37名の一揆犠牲者名の札が並ぶ。小林さんの曾曾祖父小林彦右衛門さんの名もある。
・ 地域にどのような結果をもたらしましたか。
― 税金は安くなったという結果は出たけれど、一揆が負けて、色々な処分を受けて弾圧されたダメージは大きかったと思う。
・ 県の方から、外出禁止令とか行動を規制するようなことは。
― 警察の密偵、スパイみたいなものは常に出入りして、村民の反抗がないか、見張っていたようです。ここは明治の初めの頃は、寒村で警察の駐在所が全然なかった。事件後明治15年かな、警察署の分署をつくったんです。上小瀬の宿に。そういう意味で、国から見た治安維持という体制をつくったということなんですね。
・ 今の駐在所のあるところ。
― そう。昔はもっと大きかったんですよ。今は巡査が駐在しているけれど、前は部長があそこにいた。ということは、重要視して警戒していたということだね。
・ では、ダムの反対運動の時、小林さんが代表だと知って「あの小林がまた」なんてマークされたことがあったんじゃないですか。
― 時代が違うしそれはなかったと思う。伝統的に反逆者というわけではありませんから。(笑)私は極めて民主的でおとなしい人間ですから。
・ 上小瀬で始まった抵抗は、日本では象徴的に歴史的に重要な意味があるでしょうか。
― 一つは、税金をまけさせた、明治政府が譲歩せざるを得なかった。もう一つは、その後の日本の歴史の中で、自由民権運動をさせるひとつのきっかけにはなった…と思います。
・ この一揆は、他の一揆や反対運動へ影響を与えていますか。
― ここの一揆が鎮圧されてから、その後、三重、愛知、岐阜で起こるんですけれど、その後もどんどん続いたので、政府も税金を下げるということで。当時、情報網が発達していないから、互いの一揆が影響し合っていたかどうかはわからないけれど、連絡を取り合ってやったというよりは、それぞれ同じような条件だったということだろうね。
・ では小瀬一揆が茨城の市民運動に影響を与えていることはありますか。
― それは微妙なんだよね。なぜなら弾圧がひどかったでしょ。弾圧されてそれ以降も警察の目が常に光っていたから、市民運動がのびたということはないんだな。
・ では当時は、日本各地で緊張状態があったのでしょうね。
― そうですね。地租改正をめぐって、税金が高すぎるから払えない、というような小さな紛争は全国各地にあったわけです。歴史的意味としては、民衆の反乱が起こるような状況が、この後、「国会を開設しろ」とかの自由民権運動に反影したとは思うけどね。国会開設運動につながっていく流れはあった。
・ 国会開設とは。
― その前は県会とかの地方議会というのがあって、明治22年に明治憲法ができてから国会ができたんです。以前は地方官会議といって、地方の役人が東京に集まって協議したということだった。
・ 社会的に不当な扱いが、状況の違いによって非武装の反乱であったり武装反乱になる、『幻のダムものがたり』と『万民救の旗のもとに』を通してどのようなことを理解すべきでしょうか。
― 『万民救…』のほうが結局武装反乱的闘争の形をとって、ダムのほうは平和的で暴力的なものはゼロという中で過ごしたわけなんだけど、その違いは何かというと、明治時代は、意見を上にあげる合法的な手段がなかった。文句をいえば、集まれば弾圧されてしまう。団体で押しかけるなんていうことは、もってのほか、という状況があった。ダムの頃になると、通る通らないは別として、自分の意見を上にあげることが自由にできたわけだ。言えることは言えた。その違いだよね。そして私は非暴力を選ぶべきだと思います。
・ なぜこのようなテーマを研究しておられるのでしょうか。
― 農民一揆もダムも、この地域に起こった二つの特殊な、いわば権力犯罪的な問題なんですよね。ここに起きた事件だから、地元だから調べたいというのがあります。もう一つは、国家権力、県の持っている力、権力と大衆の関係がどうなっているのだろうという、権力とは何かというテーマが常に頭にある。
・ 小林さんは、緒川の健在する歴史研究家たちのグループで、歴史の小冊子を刊行しておられます。グループの歴史研究家の皆さんも、このようなテーマの資料や年代記や警察年鑑などから研究されたりしているのですか。
― 歴史ばかりではないんだけれど、正式な名称は、郷土文化研究会が緒川地区に、大宮地区には郷土研究会があります。各々、持っているテーマは多種多様、違います。地名を研究している人もいるし、江戸時代から前の時代までの史跡を研究している方もいるんです。道標とか…。地名の珍しい名前の由来とか。資料も皆さんそれぞれ集めて、警察年鑑なんかを使うのは私くらいかな。
・ 小林さんは権力と戦争の存在関係にも興味があります。それはどういうことを示していますか。
― 最近ではアメリカとイラクの戦争があるよね。私はあれは卑怯な戦争だと思う。アフガニスタン戦争の前に、東京まで中東専門家の寺島実郎さんの講演を聞きに行ったことがあるんです。その時思ったのは、イラクとかアフガニスタンの多民族、多宗教社会、いわゆるモザイクの国家に手を付けたら内部が混乱するし、最後はめちゃくちゃになるにちがいないと。私は評論家じゃないから、そういうことを聞いて判断するしかないんだけれども。
・ 1937年、日本経済の力で、隣国を挑発した状況をどう思いますか。
― 日本は明治維新によって形の上では、欧米から遅れて、近代国家になった。当時の大久保利通はじめ政治家というのは、富国強兵・軍事力でもって世界に追いつこうとした路線を進むのだけれど、実際には日本は貧乏国で資源も何もない。だから外部へ侵略していって、そこからあがる利益で日本を強国にしようという構想方針があったと思うんですよ。だから日清戦争、日露戦争をやり、国を拡大していこうとした。昭和になってまだ物足りなくて中国に攻めていくけど、それも物足りなくて東南アジアの方に攻めて、アメリカと事を構えるようになる。
・ 小林さん自身は、権力と民衆に関してどのような研究結果に至っていますか。
― 元に戻るけれど、ダムの問題にしても農民一揆の事件にしても、国の利益のために民衆を苦しめる、そのように権力を維持していく。それに対して抵抗、反対運動が起きる。人間の権利として、このような抵抗は是認されると私は思うんです。
このあいだちょっとお話しした時に、一番重要なのは民主主義であるとおっしゃっていました。
・ フランスの哲学者ジャック・ランシエールに習って、カナダのケベックの社会学者ピエール・ムテールドは、蔑まされた環境の出身:貴族でもなんでもない生まれの乏しい人達が優遇された政治の場、それがデモクラシーであると言います。日本の歴史家である小林さんはどう思われますか。
「民主主義というのは権力と富の歴史や伝統の中断」に関してどう思いますか。
小林 そうでしょうね。民主主義の基本的な考え方というのは、金持ちも貧乏人も、持つ者も持たない者も皆、平等だということです。金持ちだから貴族だとか、貧しいから賤民ということではない。歴史の流れをずうっと見てみると、なぜ富裕層と貧困層ができるかというと、搾取があったからですよね。最初は原始共産主義で平等に働いていたのが、昔、天皇のようなものが少し能力があったとか、ずる賢かったとかで体制をつくって民衆を支配するようになって大きくなってきた。今の民主主義は貧富の差はあるけれど人間としては皆同じ平等の権利を持っている。男女同権。それが基本にあると思うんだよね。日本でも、昔は男しか選挙権がなかった。その内、税金を多く納めている(納税要件)人しか選挙権がなかった。その後、税金に関わらず20歳以上の男子全員に選挙権があるようになった。女子もなかったんだよ、戦争で負けるまで。だからそれを民主主義とはいえないでしょうね。
・ 豊穣の神々、天皇、名家、先祖伝来・伝統のやりかた、その影響力…などが、日本で重要なこととしてあげられますが。
― 今どうなんでしょうね。一般の人たちにとって、天皇が特別偉いとか、金持ちだから特別だとか考えている方は少ないんじゃないですか。
・ 天皇が特別だと、みなさん思ってないですか。
― 特別だと思っている人もいるでしょうけれど、ただ天皇というのは人権がない、選挙権がない、自由に意見を言う権利がない、恋愛も結婚も自由にできない。宮内庁に全部管理されている。プライバシーもなにもない。人間の住むところではないよね。このような伝統は民主主義には反することでしょう。
前出のピエール・ムテールドは、彼の著書『左翼の政治活動を考える』というエッセイに関する私のインタビューで、「革命(デモクラシーの中断とも言えるかもしれませんが)とは、まずなによりも断言の行為で集団の自己防衛行為です… 今日の革命とは、約束された未来へと向かうという意味よりも、むしろ”大災害を止める”ために我々が用意している道具なのです。」といいます。
Q 24 このアプローチに賛成ですか。反対ですか。
小林 日本の今の状況の中で、革命という言葉は死語に近いように感じます。革命という言葉の概念規定が私とクリスチャンでは違うかもしれないけれど、私の考えでは革命の基礎にあるのは階級理論だから、押さえつけられた下の階級が、上の階級を引っくり返して、政権を取ることが革命だと私たちは教わった。いわゆる階級闘争の結果だね。そういう意味で、日本では階級がはっきりしていないでしょ。選挙といういちおう民主的な方法で政権を変える可能性はある。現実にはなかなか難しいんだけれどもね。
・ 今までは1億総中流だったかもしれないけれど、先ほども話したように貧富の差が開いてきていることで、階級意識が生まれてしまうのではないでしょうか。
― その時は、選挙によってその方向を変えることが可能なのではないでしょうか、革命ではなくて。革命というのは、農民一揆じゃないけれど、暴力が伴わないと革命できないんですよね。ただね、選挙によって政権が逆転するような可能性はあるだろうけれど、そいういうのを「平和革命」と表明する場合がある。フランス革命とかロシア革命、キューバ革命、中国の革命… みんな武力でとっているんですよね。暴力は革命に付き物なんですよね。
「歴史は私たちに残された過去の残骸ではないし、―進歩や、ましてや文明、芸術、哲学以上のものでもない―勝利者の歴史のたぐいのものだ。『過去の出来事を歴史的なものとして明示することの意味は、『それが実際にあったとおりに』認識することではない。それが意味するものは、危機の瞬間にきらめきを発するような想起を捉えることである。』(『』内、ベンヤミン「歴史の概念について」平子友長訳)…歴史とは勝者に検閲された過去との通信を表現したもの、忘れられた苦しみ、隠れた我々の関係を表現したものだろう。」
Q 25 このヴァルター・ベンヤミンという歴史の哲学者の概念から、何か呼び起こされるものはありますか。
小林 歴史というのは生きているものだから、過去の残骸ではないよね。「進歩や、ましてや文明、芸術、哲学以上のものでもない…」とも言い切れないと思うんだけど。民衆の歴史というのは敗者の歴史で、歴史の表面には出ないよね。勝利者、その人が書く歴史だ、というのは真理だと思う。
・ 勝利者は、彼らが文明を作り上げたという傾向があると思います。文明は勝利者の民権だから。例えばトルコやアラブ諸国ではイスラムの戒律に代わって、ブルジョワ的民権が課せられ商いの掟が主流になっています。これが文明的流派で、文明的法的人間になることです。
― 民衆、即、敗者ではないんだけれど、やはり敗者の歴史があるから、歴史というのは両面見る必要があると思うんです。具体的に言うと、この「万民救…」も普通は表に出ない敗者の歴史です。ローマ大帝国の歴史だって、皇帝が何代続いてとか色々出てくるけれど、あの当時奴隷として使われていた人のことは出ない。奴隷を使って、あれを造ったこれを造った、というのはあるけれど。
・ ローマに関しては「ベン・ハー」や「グラディエーター」のハリウッド映画を待たなければ、敗者の歴史は世に出なかった。(笑)
ベンヤミンが言うように、史実を調べるだけではなくだけではなく、歴史家が危機を意識したり、危機の感性を必要とされると思いますか。
― 言葉を変えて言うならば、今までの歴史から何かを学ぶということが一つ。将来のための教訓にするということが、歴史学の研究でしょうね。
・ 小林さんが歴史家として書かれる時感じられるのは、出来事の内の危機感でしょうか、それとも思い出・想起でしょうか。
― 農民の一揆というのは、政治の矛盾が端的に現れた現象でしょ。今の政治状況と重ね合わせて考える、今は民主主義が建前の世の中になっているけれど、ずうっと見ていると増々権力の方が強くなってきて民衆の力が落ちているでしょう。そう感じません?それは危機的な状況なんだよね。それを明治の時代に照らし合わせて、これは政治の問題だけれども権力と民衆の関係の矛盾が爆発した事件という、現代との共通性を訴えてみたいということです。
・ 小林さん自身の今の危機感が、小瀬一揆へ関心を呼び起こしたということですね。過去のメッセージと現代歴史家のメッセージですね。
― そうですね。それを読み取ってもらえれば私としては幸せです。
・ 「小瀬一揆」の構想というのは、ダム問題を書かれた時にあったものですか。
― ダムが中止になった時に『幻のダムものがたり』を読んだ人に、「昔だったら農民一揆ですね」と言われたんです。「昔だったら、ダム問題の時、暴力的な蜂起、一揆的なことが起きただろう」という読み取り方をした人もいるんですよね。”昔ならば”という前提ですけど、昔ならば当然一揆が起きていたでしょうね。
著名な歴史家で エリック・J・ホブズボームは、イギリス共産党(1991年解党)入党のために生まれてしまった精神的葛藤にけりをつけるために、政治イデオロギーの志向と歴史研究への使命という理由で、1950年代に入ってすぐ共産主義の軍事化を棄却します。そして彼は歴史家という職業を選びます。 小林さんは、出身地で起こった(緒川ダム反対の舞台にもなった)小瀬一揆の記憶や市民(村民)の非常に詳細な歴史に入り込む一方、党員にはならずに、でも日本共産党に近くてらっしゃいます(*小林さんが共産党員の市議会立候補者の応援をしていたこと)。あなたの過程は、先の歴史家と違うところです。
Q 26 この選択はどう説明できますか。
小林 軍事武装化が嫌だというのはわかるよね。思想としては私は、“民主主義者”という概念はないかもしれないけれど、そういう気持ちなんだよね。共産党というのは政党としては、悪く言うのもなんだけれど、少々閉鎖的なところ、内部の情報が表に出ないところ。今の日本や常陸大宮の政治状況を考えた場合は、ある程度共産党を強くしないと政治は良くならないという考えがあるんです。
・ どのように政治的思想と歴史研究を関係づけられていますか。
― どんな人でも、ある程度の政治的な考えというのはあるでしょう。歴史家でも政治的なイデオロギーを持っていない人はいないと思う。思想的に言えば私は社会民主主義だから、共産党ではないんですよ。無理にカテゴリーに分けて証明するとすれば、フランスでいう中道左派的な考え方に近いと思う。ただ、今の日本共産党は社会民主主義的な考えになってきていますね。
・ 小林さんは制度の中で活動されて議員をやっていたから、なるほど“中道左派”ですね。
― 昔の共産党というのは、議会とか重視しなかった。終戦から間もなくの頃は、大衆革命をやるという方針だった。でも今は議会で議員を多くとって政権を取る、福祉、教育、平和外交でおとなしい政策です。だからむしろ社会民主的な考えですね。組織原則は“民主集中制”という中央集権なので、そこが気に入らないところです。今の時代には合わないと思うんですよね。政治でも地方分権の時代で、東京の問題と地方の課題は全部違うと思う、地方における自由さを認めないと共産党は伸びないと思う。
・ 政党は国の権力を征服するべく組織される、ということで私は批判的なのです。小林さんは民主主義は弱者の権利を守ると言いますが、民主主義は国家権力を常に征服しようとするのですから。民主主義の特徴はまさにこの国家を手に入れて、今度は自分が国家権力になることにあるという。私は、このゲームは暴力に導いていき、権利主義の原因となっていると思います。
― 民主主義的な方向でやれば、暴力的にはならないと思うんだよね。
・ 政党がある限り、主権を取るということが問題になると思うし、代表者を選ぶ選挙の真相を見ると、全くバカにしています。
― 古典的なマルクス主義というのは暴力革命なんですよね。マルクスの理論を政治活動に適用したのはレーニンで、革命は権力を取ることだと明快に主張している。
・ 私がここに挙げた社会哲学者の方たちは「民主主義とは権力への抵抗の場」だといっています。それは主権を取る場ではありません。
― それ、わかります。
・ 民主主義が権力取得目的でなければ、人は優しく平安でしょうが、主権が目的になると、君臨することやそれを保持することや奪われることを考えなければなりません。そこではオルターナティブ/代案・提案は受け入れられません。
― 民主主義と権力の関係でいえば、選挙で過半数の議席を取って民主主義的な政権が考えられる、そうでなければ最終的に民主主義が勝ったとは言えないと思う。いつも抑圧され押さえつけられている今の日本みたいな民主主義では、本当の民主国家だとはいえないと私は思うんだ。
・ 国家権力が強くあって欲しい企業と、国家が無い状態を好む企業があります。
― 大企業は国家に守られているから、国家が強い方がいいでしょう。今の財界見ているとそうでうよね。税金をやすくしてもらったりしてね。でも中小企業の下請けなんかは、ある面、大企業から搾取されているし、締め付けもあるだろうから、そういう人達は、自分の権利を主張できる社会のほうがいいということになるんじゃないでしょうか。
・ 私は民主主義の場とは言わずに、平和の場と言いますが、ここでの中小企業が担う役割は大きいと思います。企業というのは、いつも与党や保守派に属していると思いがちですが、実はそうでもないと、様々なやり方でやる可能性があると思うからです。
― 私は、中小企業の傾向というのはよくわからないんですけど、だいたい企業というのは自民党支持が多いですよ。製材所や工場がここにもありますけど、その人たちは自民党支持派です。
・ なぜでしょう。
― 自民党に守られているという考えがあるし、労働者(雇われ人)は共産党なり社会党なり支持だけれど、経営者はそれとは違うんだというエリート意識があると思うんですよね。大企業でも小企業でも経営者の意識の質は違わない。労働者を使っているという意識が自民党を支持させ、ちょっと変わっていると民主党支持くらいで終わってしまうでしょう。
・ では経営者で共産党支持者はいないのですか。
― 企業者で共産党支持者はよほど変わっている人でしょうね。
・ 経営者で仏教徒の人も知っていますが、安い商品を提供することで企業をつぶさないようにするのは手かもしれませんが、今では資本主義帝国になってしまいました。キリスト教徒の経営者も、資本主義です。…それについて誰も何も言いません。地球上の60億の人達がそれぞれ彼らの文化を保護できるようになるのは難しいことです。
― 色んな考え方、宗教、民族、それらをお互いが尊重できるような国家間のつながりができれば戦争なんか本当は起こるわけはないんだけどね。一つの価値観を相手に押し付けることで争いが起きる、アメリカの大国論理で世界を統一しようなんてとんでもない。アメリカの民主主義を押し付けられたイラクも分裂してあんなふうになってしまう… これは一番悪いことだと思うんだよね。
・ 緒川地区は平和ですか。
― 細かい問題はあるけれど、基本的には平和だね。
ありがとうございました。
 緒川沿いののどかな田園
緒川沿いののどかな田園《インタビュー終わり》
『幻のダムものがたり』小林茂氏インタビュー【1】へもどる
“日本の非暴力の政治的市民運動と自由”、“平成の大合併”に関するインタビューなど、フランス語のページ。
[ 1 ] Japon : Reforme, Grande Fusion de Heisei, Dissolution
[ 2 ] LIBERTES et ACTIONS CIVILES ET POLITIQUES NON VIOLENTES AU JAPON, Tableau national et Carte Regionale d'Ibaraki de la Grande Fusion de Heisei
[ 3 ] "DES BRIOCHES, DES EAUX ET DES CHOUX", Kusatsu et Tsumagoi
[ 4 ] "La Grande Fusion de Heisei s'oppose au futur du Japon !", Hiroshi Itoh, maire de la ville de Kutchan, Hokkaido
[ 6 ] "Ce que chacun peut réellement faire ou être", ou évaluer la justice dans un contexte de décroissance, "YAMBA, le plus lourd fardeau des contribuables de l'histoire des barrages du Japon"